
|
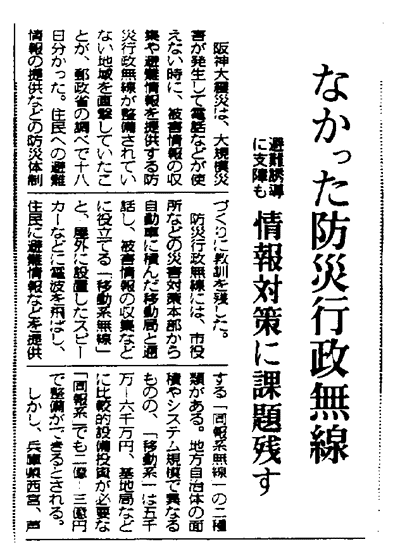
図1市町村防災行政無線関連記事(毎日新聞1月19日朝刊)
おそらく、このように事前の準備が必ずしも十分でなかったのは、被災地域の住民ばかりでなく行政機関も、東京や静岡は大地震が怖いけれども、関西には大地震はやってこないという安心感があったためと思われる(図1)。 こうした無線網の欠如に加えて、今回の震災ではほかにも深刻な事態が起こった。それは、都道府県防災行政無線の障害である。 地震が発生したとき、兵庫県庁には平成3年に80億円の巨費を投じて導入した、衛屋通信による防災情報システムがあった。これは県下の市町村から被害情報を収集し、それをまとめて自治省消防庁に伝達するシステムであり、災害情報の収集・伝達の中心的位置を占めているが、地震のために県庁の12階にあったこのシステムの端末パソコンやファクシミリが床に落下するなど、足の踏み場もないほど部屋中が散乱してしまった。また、停電しても稼働するように自家発電装置がついていたが、冷却用の水槽が地震で破壊されてしまい発電装置が自動的に停止したうえ、バックアップ用の蓄電池も容量を使い果たしてしまったため、1O時23分から12時5分までの約2時間まったく動かなくなってしまった。また、市町村のあいだの情報連絡はある程度可能だったようであるが、西宮市などいくっかの市でも、バラボラアンテナの方向がずれたり、自家発電装置が故障したりしたため、このシステムを通じての情報収集・伝達がきわめて難しくなったのである。このことは、防災情報システムの整備にあたってはシステム本体ばかりでなく、端末パソコンや自家発電装置・冷却用水槽・パラボラアンテナなど周辺装置も含めた、システム全体の総合的な耐震化が必要だということを示すものといえよう(図2)。 今回の震災における防災情報システムの被害はまだあり、神戸市消防局でも、ポートアイランドに設置してあった高所監視カメラが地震の振動により作動しなかったとか、神戸
前ページ 目次へ 次ページ
|

|